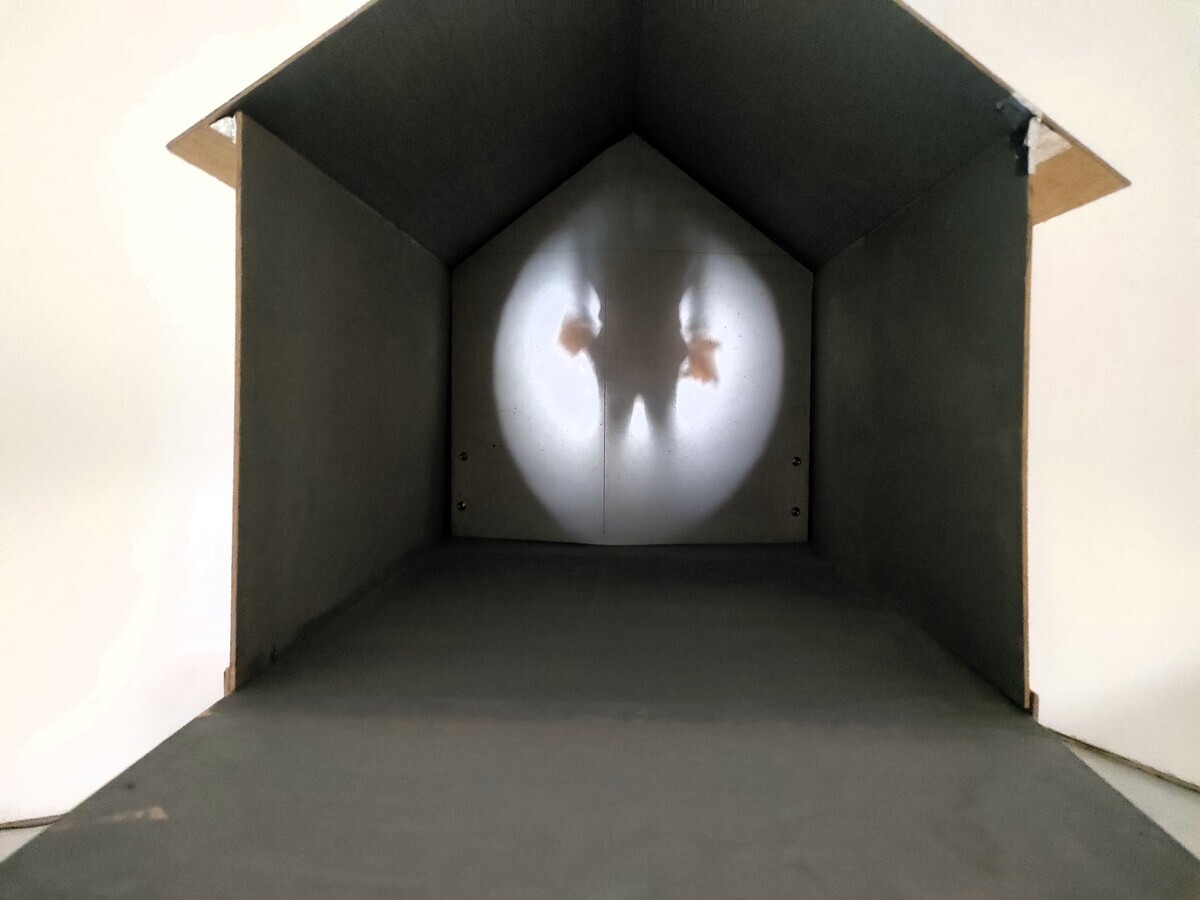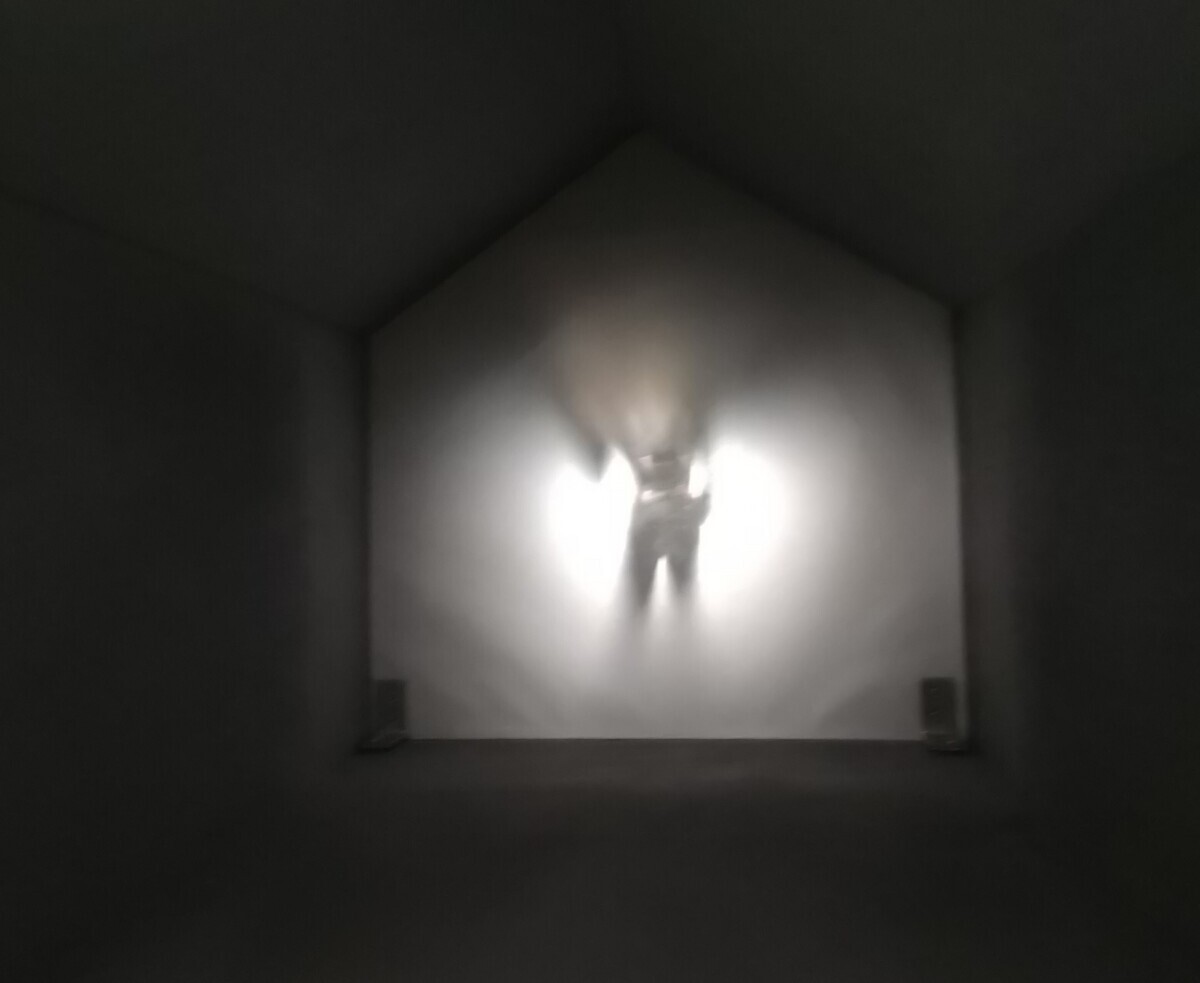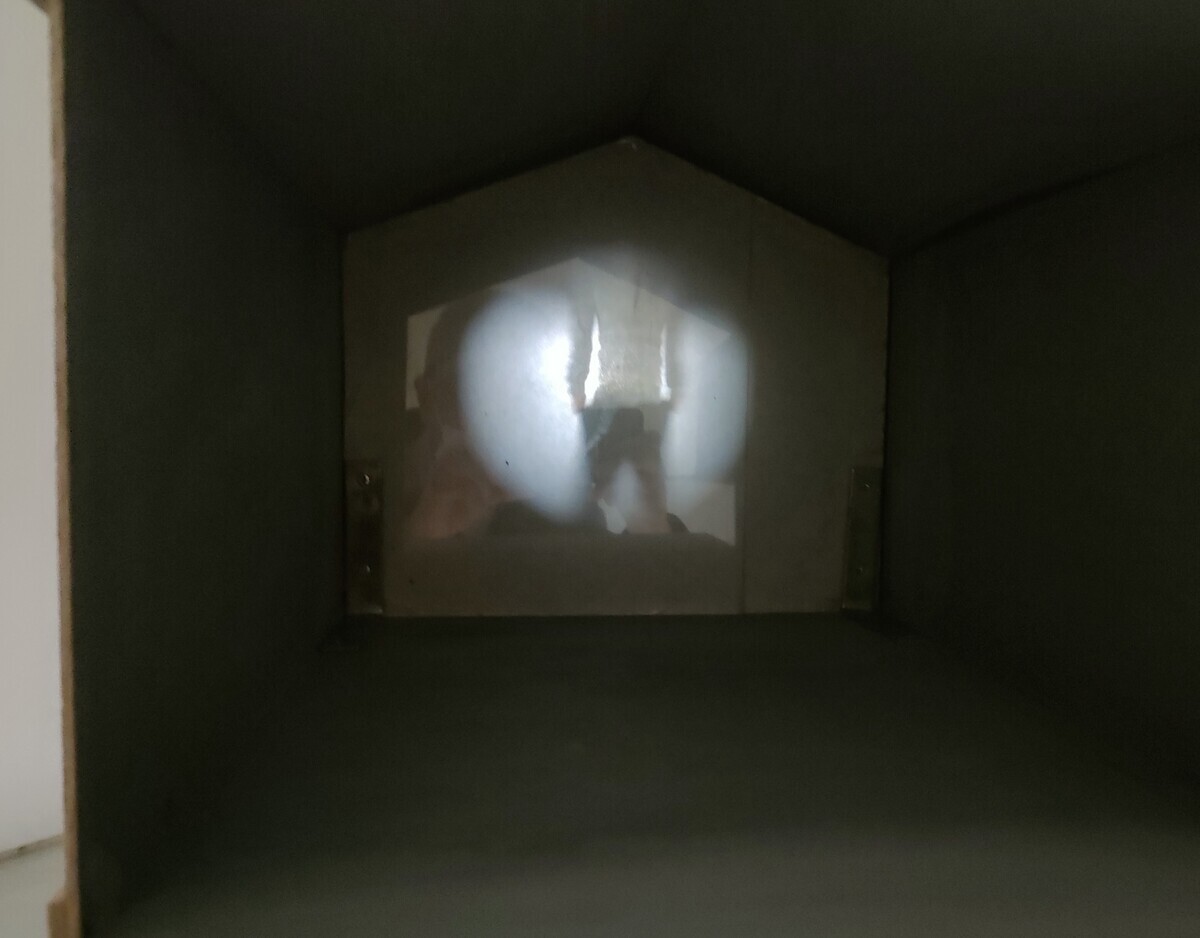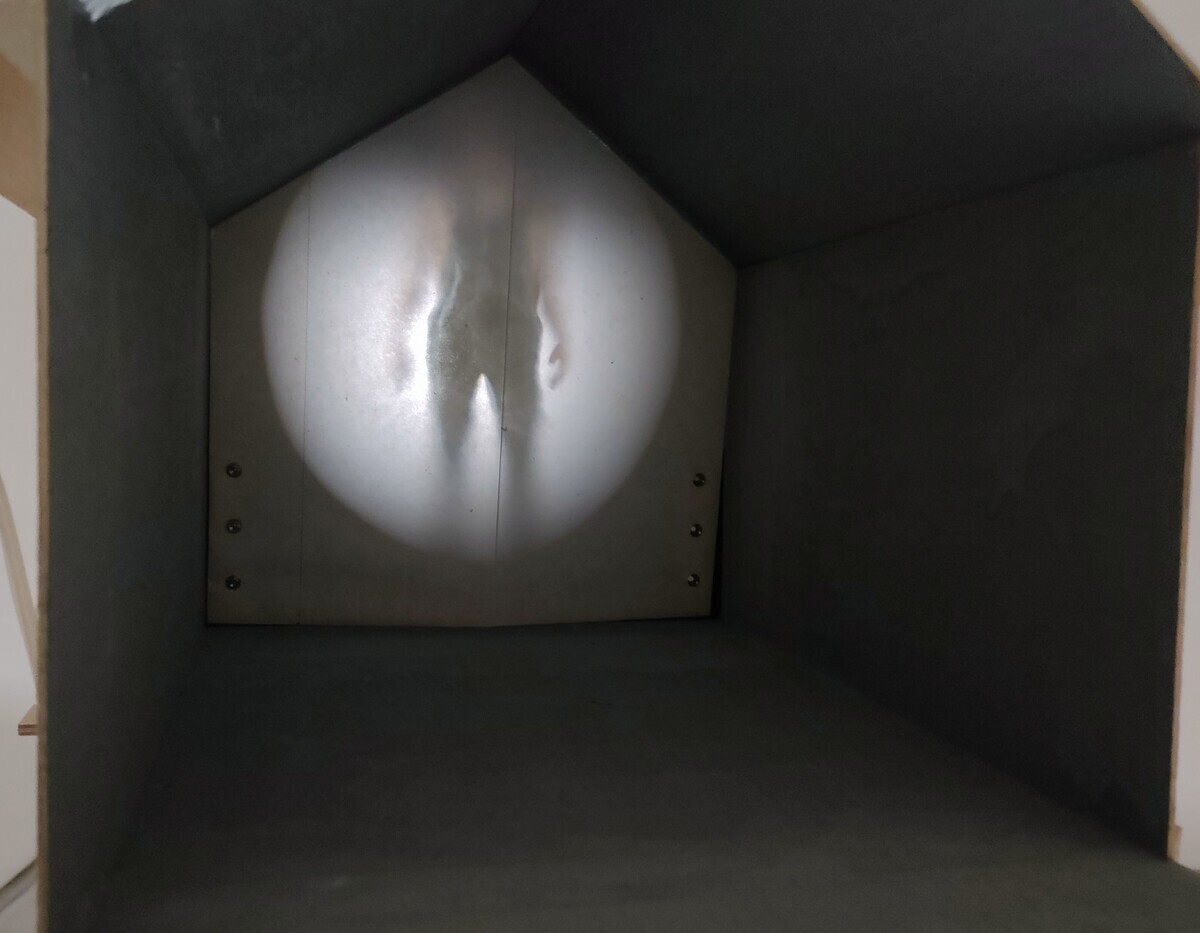イザベラ・バード『日本奥地紀行』(平凡社ライブラリー)を読む。イザベラ・バードは1931年イギリス生まれ、明治11年、48歳のとき来日して6月から9月にかけて日本人従者をたった1人連れて東京から北海道へ旅行している。その詳細な記録。道路事情は最悪で、人力車や馬、徒歩、ときには川を泳いで渡っている。
従者は18歳の青年で従者兼通訳として終始イザベラ・バードを補佐した。旅行の行程は東京~粕壁~日光~会津盆地~新潟~小国~置賜盆地~山形~新庄~横手~秋田~青森~津軽海峡~函館~室蘭~白老・平取(アイヌ部落)~内浦湾~函館~(船)~横浜。
明治11年という早い時期に女一人で半未開とも言い得るような地を旅行したなんて、ほとんど英雄譚と言っても良いくらいだ。当時の貧しい農民生活が実際に体験した外国人の眼で描写される。
横浜に上陸して最初に受けた印象は、浮浪者が一人もいないこと、街頭には、小柄で、醜くしなびて、がにまたで、猫背で、胸は凹み、貧相だが優しそうな顔をした連中がいたが、いずれも自分の仕事を持っていたというもの。
日本の治安について、「私は奥地や北海道(エゾ)を1200マイルにわたって旅をしたが、まったく安全で、しかも心配もなかった。世界中で日本ほど、婦人が危険にも不作法な目にもあわず、まったく安全に旅行できる国はないと私は信じている」とバードは書いている。
旅館はみすぼらしく、プライバシーがなく、蚤が大量にいて悩まされる。障子は穴だらけで、どの穴にも人間の眼がある(つまり覗かれている)。また外国人を見るために多くの群衆が集まってくる。人垣ができ、屋根の上にも野次馬が群がる。
宿の奥さんに年を聞くと、50歳くらいに見えたのに22歳だった。老け込むのが早い。
バードはアイヌに強い興味を持っていて、その生活を調査している。アイヌに関するバードの記録が詳しいので、『ゴールデンカムイ』の参考文献にもなっているという。アイヌの女について、バードは書く。「彼女(酋長の母)の表情は厳しく近寄りがたいが、たしかに彼女はきれいである。ヨーロッパ的な美しさであって、アジア的な美しさではない」。
アイヌに関する記載は100ページ以上に及ぶ。これは本書のおよそ2割を占める。バードのアイヌに対する印象は極めて好意的だ。
さて、明治11年という極論すれば半未開の日本奥地を、従者一人を連れて女一人で北海道まで旅行したイザベラ・バードというイギリス人はほとんど英雄と言って良いのではないか。優れた紀行文学である。






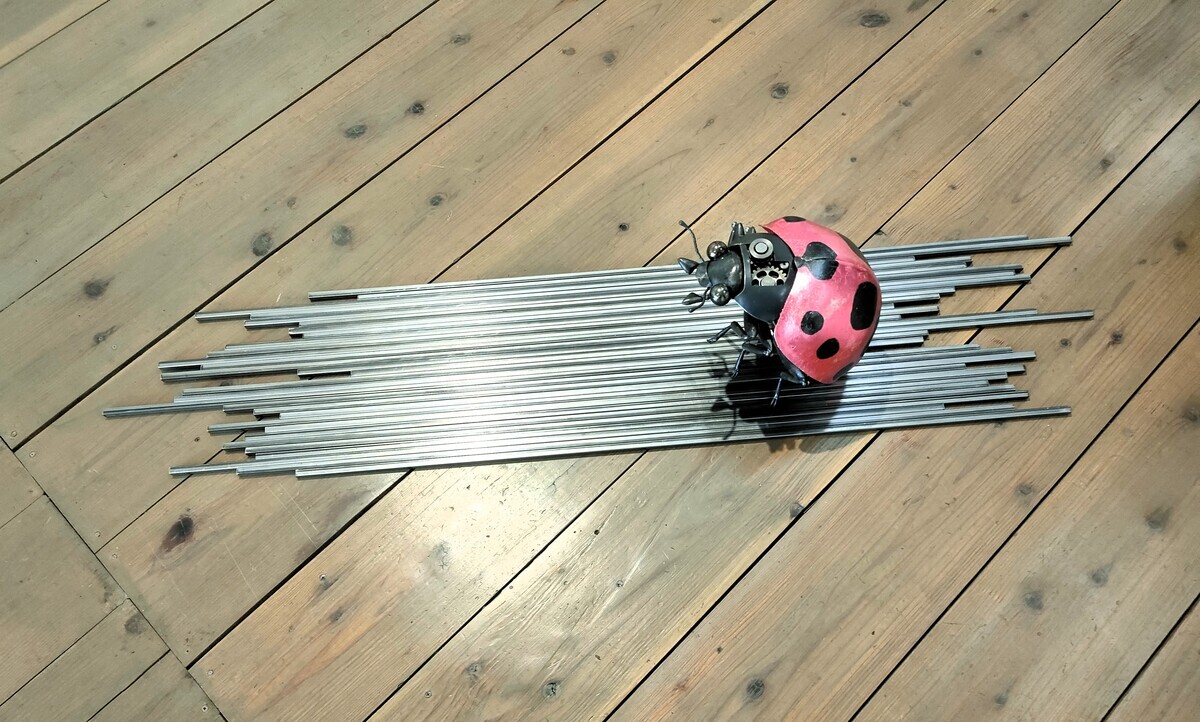



 このスカイシリーズが面白い。サイアノタイプ(青写真)とシルクスクローンを組み合わせている。1枚の写真の一部をサイアノタイプで刷り、それ以外を
このスカイシリーズが面白い。サイアノタイプ(青写真)とシルクスクローンを組み合わせている。1枚の写真の一部をサイアノタイプで刷り、それ以外を